
アルファベット(GOOGL)は、世界で広く利用されている検索エンジン・サイト「Google」を運用する企業です。
検索サイトでの広告収入などで収益をあげている他、昨今では、自動運転などの先進的な事業も行っています。
本記事では、アルファベット(ティッカーコード:GOOGL)の企業の特徴や業績、また現在株価や配当利回りなどを解説していきます。
米国株の取引手数料を余分に払っていませんか?
米国株の取引コストは、日本株や投資信託の取引コストよりも割高です。
手数料・コストは、投資家への確実なマイナスリターンとなり、投資パフォーマンスを悪化させるので、手数料を安くすることが、投資の成功への確実な近道です。
そこでオススメの証券会社が、米国株の取引手数料が0円・無料のDMM.com証券「DMM株」です。
- 米国株の取引手数料が無料!0円!
*SBI証券や楽天証券などは約定代金の0.45%(税込0.495%)の手数料が発生 - 最短で当日のNY市場から取引できる!
- 米国株が信用取引の担保になる!
*ネット証券市場初! - 今なら、口座開設キャンペーンで、最大2,000円!
 サイト管理人
サイト管理人米国株を取引する方には、必須の証券会社の地位を築きつつあります!
今なら、口座開設キャンペーンで、日本株の取引手数料も1ヶ月無料になるうえ、最大2,000円がもらえます。
そのため、米国株の取引を行う方で、DMM.com証券「DMM株」の口座をお持ちでない方は、この機会に口座開設しておきましょう!
最短・即日で、口座開設が完了して、その日の米国市場から取引が始められます!
\ キャンペーン参加はコチラ /
口座開設費・維持費無料!
最短で即日から取引可能!
アルファベット(GOOGL)とは?
アルファベット(GOOGL)は、インターネット検索サイト「Google」を運用するGoogle Inc.の持ち株会社です。Google Inc.の他、Google Capitalなど様々な子会社で構成されています。
以下、アルファベット(GOOGL)社の特徴や業績、また株価や配当利回り等を見ていきます。(業績データなどはyahoo finaceより引用しています。)
企業の特徴・業績
Googleは、1998年に創業した企業です。2015年に持ち株会社「Alphabet」に移行し、Google自体はAlphabetの完全子会社になりました。創業以来、検索エンジンで有名になり、その後、GmailやGoogle Mapなど周辺分野を開拓してきています。
昨今では、youtubeなどの買収により、広告収入のチャンネルを増やしたことが話題となりました。圧倒的な検索シェアで広告収入を収益の柱としていますが、近年は自動運転やクラウド事業など先進的な分野にも積極投資しており、今後の展開が注目される企業です。
米国を代表する株価指数「S&P500」に採用されており、FANG(ファング)銘柄の一角として、米国だけでなく世界中の個人投資家に注目されています。
また、アルファベットのここ数年の業績は、下表のようになっています(Google時代の業績と合成)。売上高・営業利益ともに順調に伸ばしています。
| 項目 | 2018年 12月期 | 2017年 12月期 | 2016年 12月期 | 2015年 12月期 | 2014年 12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (単位:百万ドル) | 136,819 | 110,855 | 90,272 | 74,989 | 66,001 |
| 営業利益 (単位:百万ドル) | 26,321 | 26,146 | 23,716 | 19,360 | 16,496 |
| 純利益 (単位:百万ドル) | 30,736 | 12,662 | 19,478 | 16,348 | 14,136 |
| EPS:1株当たり益 (単位:ドル) | 44.22 | 18.27 | 27.88 | 23.59 | 20.57 |
直近の決算・決算速報
アルファベット(GOOGL)の最新の決算は、2019年7月に発表された4-6月期決算です。結果は、以下のようになっています。
- 売上高:38,940百万ドル
- 当期利益:9,950百万ドル
市場予想を上回る売上高となりました。今後どのように推移するか不透明なものの、2019年1月-3月は市場予想に届かず、株価を下げており、成長鈍化が懸念されていただけに安心感が出ました。
(参考:アルファベットの4-6月売上高、市場予想上回る|ブルームバーグ)
アルファベット(GOOGL)の株価・配当利回り
アルファベット(GOOGL)の株価や配当利回りは、以下のようになっています。収益を成長分野へ積極的に投資しているため、配当金はありません。
また、アルファベットは、議決権の有無でクラスA株(GOOGL)とクラスC株(GOOG)の二種類があります。
- 株価:1,349.33ドル
- 配当利回り:0.0%(無配)
- PER:30.51倍
配当利回りが高い米国株は、以下の配当利回りランキングをご参照ください。
以下、アルファベット株など米国株を安く取引できる、お得なオススメ購入先(証券会社)を解説していきます。
米国株の取引は、売買手数料・為替手数料など、日本株の取引と比較してコストが割高になりがちなので、手数料の安い証券会社を選び、相対的な投資パフォーマンスの向上を目指しましょう。
最低1,000円!アルファベット(GOOGL)株を安く購入する方法は?
アルファベット株など、米国株への投資・取引は「PayPay証券」がオススメです。
例えば、1株を買うのに約30万円が必要な「アルファベット株」も、最低1,000円から好きな金額で購入できます。
PayPay証券を利用すれば、初心者の方、少ない投資金の方でも、銘柄や買うタイミングを分散して投資できます!
- 最低1,000円から米国株が買える!
- 好きな金額で米国株の取引ができる。
- 24時間いつでも取引できる!
- キャンペーンで最大1万円もらえる!
→ PayPay証券の公式ページを確認
米国株を少額投資できる証券会社は「PayPay証券のみ」です。
今なら、1周年記念「口座開設キャンペーン」で最大10,000円がもらえるので、この機会に口座開設しておくと良いでしょう。
\ キャンペーン参加はコチラ /
*口座開設費・維持費無料
*申込みはカンタン3分!
PayPay証券のキャンペーンや口座開設の方法は、以下の記事をご参考ください。
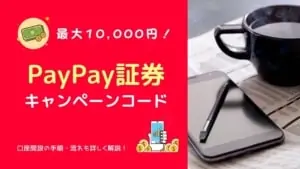
昨今のフィンテックの普及で、少額(1万円や10万円から)でも、たくさんの銘柄に分散投資が行えるようになりました。
特に、最低1,000円から金額指定で「米国株」が購入可能なPayPay証券は、米国株へ分散投資したい方にピッタリです。
投資資金が1万円でも、最大10銘柄に分散投資が行えます。
PayPay証券の特徴・メリット
PayPay証券の特徴は、少額(1,000円)からスマホで手軽に株取引ができる点です。
ネオモバやLINE証券、フロッギーなど他の少額投資サービスの場合、日本株しか取引できませんが、PayPay証券であれば米国株の取引も行えます。
- 1,000円から株投資ができる!
- 米国株にも投資可能
- IPOにも少額投資が可能
- スマホでカンタン操作!
金額ベースでの米国株の取引、少額での米国株の取引が可能な点が「PayPay証券」の大きな魅力です。日本株への投資であれば「1株からIPOに参加」することも可能です。
\ キャンペーン参加はコチラ /
口座開設費・維持費無料
申込みはネットで完結!
1万円から運用できる高配当ポートフォリオ
PayPay証券を利用すると、以下のような高配当ポートフォリオを「1万円」から運用可能です。
最低1,000円から1つの銘柄を購入できるので、投資資金を増やせば、さらに多くの銘柄に分散投資が可能で、「積み株」を利用すれば、積立投資も可能です。
高配当ポートフォリオの例
| 銘柄名 | 配当利回り |
|---|---|
| アルトリア・グループ | 8.10% |
| エクソン・モービル | 7.42% |
| AT&T | 6.85% |
| シェブロン | 5.61% |
| IBM | 5.25% |
| アッヴィ | 4.90% |
| ベライゾン・コミュニケーションズ | 4.32% |
| コカ・コーラ | 3.49% |
| ジョンソン&ジョンソン | 2.81% |
| P&G | 2.65% |
コカ・コーラは、他の銘柄と比較すると、配当利回りは低いですが、増配継続年数が長いことで有名です。
このように、PayPay証券を利用する事で、投資資金「1万円」からでも、アメリカの増配株に分散投資をすることが可能になります。
PayPay証券を利用して、毎月「配当金」をもらう方法は、以下のページをご参考ください。


