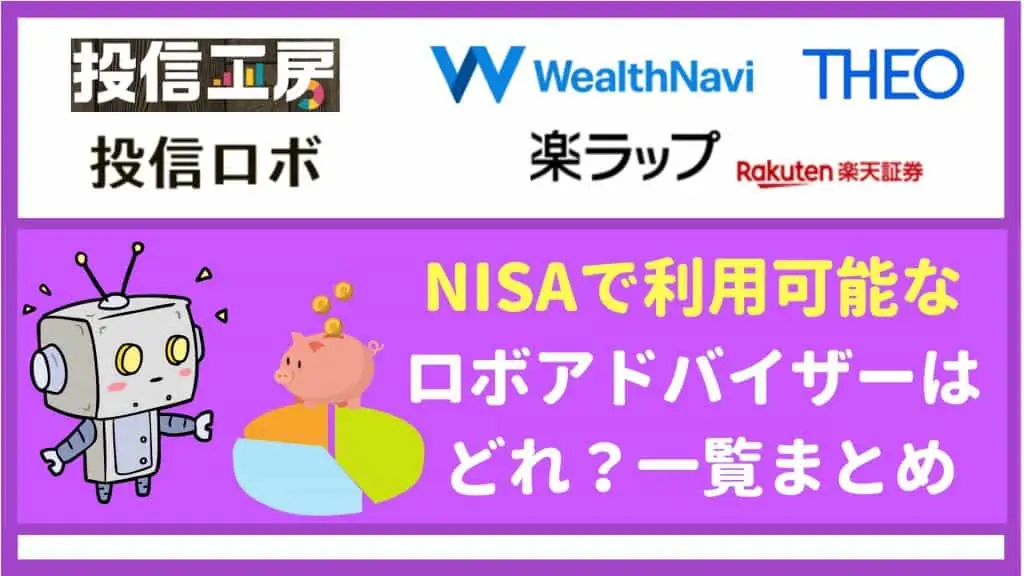##
 サイト管理人
サイト管理人初心者の方でも分かるように、シンプルかつ網羅的に解説していきますので、ぜひご覧ください。
つみたてNISAは、これから投資・資産運用を始める方が、覚えておくべき制度の一つです。
つみたてNISAを活用すれば、投資利益にかかる税金を非課税にする事ができます。
- 投資利益が非課税
- 非課税期間が20年
- 非課税枠が年間40万円
→ 最大800万円(=40万円×20年) - 金融商品が厳選されている
 サイト管理人
サイト管理人通常、20%程度かかる税金が「非課税(税率0%)」になる点が最大のメリットです。
このようにメリットが大きい「つみたてNISA」ですが、
- どうやって始めれば良い?
- どんな制度?デメリットは?
- 何に投資信託した良いの?
など、様々な疑問があると思います。
そこで、本記事では、つみたてNISAの基礎知識やメリット・デメリット、さらに実際の始め方を徹底解説していきます。
 サイト管理人
サイト管理人実際に続けてみて思ったこと・感じたことも紹介していきます。
##ガイド(始め方、基礎、投資信託)
ブログ解説①つみたてNISAの制度を知ろう!
はじめに、つみたてNISAの制度概要、一般NISA・iDeCoとの違いを比較し、メリット・デメリット等をまとめていきます。
 サイト管理人
サイト管理人実際に始める前に、つみたてNISAのメリット・デメリットを理解しておきましょう。
つみたてNISAの制度概要
積立NISA(つみたてニーサ)とは、2018年からスタートした新たな小額投資非課税制度です。
現行のNISA(一般NISA)同様、金融商品の値上がり益や分配金など投資益が非課税になる制度です。
日本在住の20歳以上の方が対象で、年間の利用限度額(投資上限)は40万円となっており、現行NISAの年間限度額120万円よりも小額ですが、その分、非課税期間が20年間と長期で非課税メリットを受けられる点が特徴です。
- 対象者:20歳以上(日本在住)
- 利用限度額:40万円
- 非課税期間:20年
⇒累計非課税限度額:800万円(=40万円×20年)
一般NISAとつみたてNISAの違い・比較
現行NISAとの大きな違いは「非課税期間」と「年間の非課税枠(投資限度額)」です。
非課税期間は、現行NISAが5年であるのに対し、積立NISAは20年間も非課税メリットを受けられます。
その分、積立NISAの年間の非課税枠は40万円と少なくなる点が両者の違いです。
| 項目 | 積立NISA | 一般NISA |
|---|---|---|
| 対象者 | 20歳以上(日本人) | 20歳以上(日本人) |
| 利用限度額 | 年間40万円 | 年間120万円 |
| 非課税期間 | 20年 | 5年 |
| 運用できる商品 | 金融庁が認める投資信託・ETF | 国内外の個別株・ETF・REIT、および投資信託 |
また、利用できる金融商品にも違いがあります。現行NISAは、ほとんどの金融商品が利用可能でしたが、積立NISAは、金融庁が認めた投資信託のみが対象商品となっています。
つみたてNISAは運用期間が20年と長期になるため、利用できる金融商品も金融庁のチェックが入り、認められた商品のみが対象となるようです。
「おすすめ商品」のところで詳しく解説しますが、手数料の安いインデックスファンドやアクティブファンドが対象となっている点が特徴です。
【徹底比較】メリット・デメリット
ここで、つみたてNISAのメリット・デメリットについて、まとめておきます。
下表は、積立NISAのメリット・デメリットをまとめたものです。
非課税期間・年間非課税枠・取扱商品の3つの点で、現行NISAとの違いがあり、メリット・デメリットが分かれてきます。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・非課税期間が20年 ⇒現行NISAよりも非課税メリットを長くうけられる ・非課税枠が最大800万円 ⇒現行NISAは最大600万円金融商品がはじめから厳選されている | ・年間限度額(40万円)が一般NISA(120万円)より少ない ・取り扱える商品が少ない |
基本的には、投資信託を小額積み立てるなど長期投資を行なう方は積立NISAの方が向いており、中期での値上がり益などを狙う方は、現行NISAの方が良いでしょう。
また、積立NISAは金融商品に制限があるので注意が必要ですが、金融庁が長期の運用に適合していると認める商品が厳選されているという意味で、安心感はあります。
個人型確定拠出年金(iDeCo)との違い
最後に、個人型確定拠出年金(iDeCo)との違いを見ていきます。
基本的に、iDeCoは、60歳まで運用資金が引き出せないなど年金運用としての性質がある制度で、下表のような違いがあります。
| 項目 | つみたてNISA | iDeCo |
|---|---|---|
| 対象者 | 20歳以上の日本人 | 20〜60歳の日本人 |
| 利用限度額 (年間) | 積立:40万円 現行:120万円 | サラリーマン、自営業など立場によって異なる (年14.4万〜81.6万円) |
| 非課税期間 | 積立:5年 現行:20年 | 60歳まで |
| 税制優遇 | 譲渡益非課税 受取時非課税 | 譲渡益非課税 掛け金非課税 ⇒ 所得・住民税軽減 受取時課税 ⇒ 退職所得控除等が適用され軽減 |
大きな違いは、NISAの非課税メリットが運用益だけであるのに対し、iDeCoは掛け金で所得税や住民税が軽減される点です。そのため、非課税メリットはiDeCoに軍配が上がります。
ただし、iDeCoは60歳になるまで、原則的に運用資金が引き出せないので、その点には注意が必要であり、運用の自由度はNISAの方に軍配が上がります。
つみたてNISAの制度【まとめ】
ここまで解説してきたように、積立NISAは、2018年1月から始まる新たなNISA制度の1つです。
一般NISAのデメリットととも言えた、非課税期間の短さを解消し、20年間非課税メリットを受けられるものとなっています。
非課税期間が長い分、年間の投資限度額は少なめですが、小資金を長期で積立運用される予定の方には、ぴったりの制度設計とも言えます。以下では、積立NISAにあった商品の選び方などを解説していきます。
ブログ解説②つみたてNISAの始め方
つみたてNISAの特徴を抑えたところで、つみたてNISAを始める具体的な手順・流れを解説していきます。
 サイト管理人
サイト管理人積立NISAの証券口座・投資商品の選び方などは、その都度、解説していきます。
つみたてNISAで投資を始める手順は、以下の3つのステップがあります。
- つみたてNISA用の口座開設
- 金融商品(投資信託)を選ぶ
- 投資信託を購入・積立
始めに、つみたてNISA向けの証券会社の口座を開設します。
証券会社は、口座開設費・維持費は全て無料で、投資情報や金融商品の最新情報が得られるため、口座開設をしておきましょう。
 サイト管理人
サイト管理人証券会社によっては、お得な口座開設キャンペーンを開催しています。
口座開設後は、つみたてNISAで運用する投資信託を決定し、証券会社で購入する流れとなります。
以下、各ステップについて、詳しく解説して行きます。
ステップ①:証券会社(金融機関)の口座開設を行う
つみたてNISAで投資を行うには、証券会社や銀行などの金融機関の口座開設が必要です。
つみたてNISA向けのオススメ金融機関は、ズバリ「ネット証券」です。
ネット証券であれば、ネット上で低コストで「つみたてNISAで投資信託の運用が行えます。
ネット証券の中でも、特におすすめなのが「楽天証券」です。
楽天カード(クレジット決済)で投資信託の積立が行え、購入額の1%分がポイント還元されます。
このポイントは、楽天市場や楽天ペイ等を利用してネット上やリアル店舗で1pt=1円として利用できる他、ポイントで投資信託の購入も行えます。
- 積立額の1%分をポイント付与
→ 確実な1%の利益 - 貰ったポイントで投資信託の購入が可能
→ ポイントで再投資ができる
このように、つみたてNISAを楽天証券で始める事で、非課税メリットを享受するだけでなく、楽天カード決済により1%の利益も得る事が可能になります。
楽天証券では、現在、口座開設キャンペーンで「もれなく」現金1,000円がプレゼントされたり、各種取引で最大25,000円相当のポイントや高額現金が貰えます。
現金1,000円は、楽天証券・楽天銀行の同時口座開設&連携だけで、ノーリスクで貰えるお得なキャンペーン内容です。そのため、口座開設を行っていない方は、この機会に口座開設を行うと良いでしょう。
楽天証券・楽天銀行の同時開設&連携の方法やキャンペーンの詳細は、以下をご参考ください。
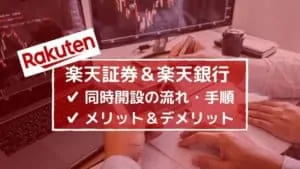
ステップ②:投資する商品(投資信託)を選ぶ
つみたてNISAは、金融庁からお墨付きがついた投資信託(主にインデックスファンド)、またETFが投資対象になります。
100以上の対象銘柄がありますが、楽天証券などネット証券では、以下のようなファンドが人気となっています。
| 順位 | 銘柄名 | 管理コスト (信託報酬) |
|---|---|---|
| 1位 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.0968% |
| 2位 | 楽天・全米株式インデックスファンド | 0.162% |
| 3位 | eMAXIS Slim全世界株式 | 0.1144% |
| 4位 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 0.1023% |
| 5位 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 0.212% |
 サイト管理人
サイト管理人全世界や米国の株式市場への投資を目的としたインデックスファンドがランキング上位となっています。
つみたてNISAで運用する投資信託の選び方や最新のランキング等は、以下のページをご参考ください。
ステップ③:投資信託を購入・積立する
一番お得に楽天証券で積立NISAを始める具体的な方法は、以下の記事をご参考ください。
→
ブログ解説③:つみたてNISAのおすすめ投資信託は?【2021年最新版】
積立NISAのメリットを活かすため、以下の3点に留意して金融商品を決めるとよいでしょう。
ただし、積立NISAの場合、金融庁のチェックがすでに入っている商品なので、基本的に、そこまで変な商品を選ぶことはないでしょう。
- 低コストの商品
- 分散された商品
- リターンの高い商品
 サイト管理人
サイト管理人以下、各ポイントを解説していきます。
手数料の安い商品を選ぶ
まず重要な点が、手数料の安い金融商品を選ぶことです。積立NISAの商品は購入手数料は無料ですが、信託報酬と呼ばれる保有期間中に年率1%以下程度で取られる手数料があります。
この手数料は、投資家への確実なマイナスリターンとなり、投資パフォーマンスを悪化させるので、なるべく信託報酬の安い金融商品を選ぶ点が重要です。
分散投資
積立NISAは、運用期間途中でも売却できますが、長期運用が基本となります。そのため、値動きの激しい商品ではなく、分散の効いた値動きの安定した金融商品を選ぶこともポイントとなります。
リターンが期待できるもの
NISAの非課税メリットを活かすには、運用資産の中でリターンが期待できる商品を積立NISAで積み立てしましょう。例えば、株式・債券ファンドを積み立てる方の場合、株式ファンドを積立NISAに割り当てることで、非課税メリットを最大限行かせる可能性が高まります。
ここまで解説してきた3点がNISAの商品を選ぶうえでのポイントになります。一般的には、日本の株式市場や海外の株式市場に幅広く分散投資ができるインデックスファンドが無難です。以下に、投資先別の低コストインデックスファンドをまとめましたが、ほとんどの商品が信託報酬0.5%以下となっています。
| 投資先 | ファンド名 | 信託報酬(税込) |
|---|---|---|
| 日本株 | たわらノーロードTOPIX | 0.1944% |
| ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.1944% | |
| eMAXIS Slim国内株式インデックス | 0.1944% | |
| 全世界株 | SBI全世界株式インデックスファンド | 0.139% |
| eMAXIS Slim全世界株式 | 0.142% | |
| 世界経済インデックスファンド | 0.540% | |
| 米国株 | iFree S&P500インデックス | 0.243% |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.0965% | |
| 先進国株 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 0.216% |
| ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.216% |
基本的には、インデックスファンドを選ぶのが無難ですが、ひふみプラスのように、口コミや評判も良く、長期でインデックスを上回るアクティブファンドもあるので、好みによっては、そちらを選択しても良いかもしれません。
選んだ投資信託を購入する
つみたてNISAで運用する投資信託が決まったら、投資信託の購入、または積立設定を行います。
今回は、当サイトでオススメの楽天証券「楽天カード決済による積立投資」で、つみたてNISAを行う手順・流れを解説して行きます。
楽天証券でのカード積立やポイント投資の詳しい方法(図解付き)は、以下の記事をご参考ください。